古くから言われる杣夫(そまふ)とは、林業従事者のことを指します。
杣人(そまびと)とも呼ばれます。
同じ意味の林業従事者として「きこり」の方がよく使われていますよね。
コチラの方が、なじみがあるのではないでしょうか?
木を伐りだして丸太に加工する作業を「造材(ぞうざい)」と呼びます。
同じ意味ですが、正式には「素材生産(そざいせいさん)」と言われてます。
「伐木」や「伐り出し」と言われることもあります。
林業の造材作業とは、具体的にどんな仕事なのでしょうか?
林業造材の仕事内容

造材とは、立木の状態から運搬するために丸太に加工する作業です。
「立木から丸太になるまで」を指します。
山林立木の状態では見て楽しむだけです。
丸太に加工してはじめて付加価値が産み出されます。
では、造材はどんな仕事内容に枝分かれしているのでしょうか?
立木を伐り倒す人

立木を伐って倒すことを「伐倒(ばっとう)」と言います。
いわゆる伐採です。
それを専門にする林業従事者は「山子(やまご)」と呼ばれています。
かなり古いゲーム”きこりの与作”のイメージどおりです。
斧やノコギリで立木を伐り倒すのが仕事です。
ただし、現代の伐倒道具はチェーンソーや高性能林業機械です。
ご想像のとおり、伐倒はとても危険です。
経験や安全知識、技術が必要です。
災害が最も多い「かかり木」

林業重大災害事故で最も多い原因の一つに「かかり木」があります。
事故例には、伐倒作業がよく関連します。
しかも死亡事故が多く、かかり木の処理について必ず安全講習があります。
現在は高性能林業機械により伐倒作業も機械力の範囲が広がりました。
機械伐倒は確かに安全です。
でも、地形や現場状況によっては重機が入れない箇所も多くあります。
人力での伐倒は今も続いており、かかり木処理はとにかく安全第一です。
倒した樹木を集めて運ぶ

伐倒後は丸太を積み上げておく場所に運ばなくてはなりません。
計画どおりにうまく伐倒しても、伐倒木はそれなりに山腹に散らばります。
それらを一本ずつ集めて、丸太の集積箇所に運ぶことを集材と言います。
運ぶといっても、立木一本は1t以上の重さがあります。
山林の地形や土質がさまざまであり急傾斜地では危険が伴います。
集材は造材に要する時間の決め手になるほどの重要工程です。
作業の着手前に、安全で効率よく計画をたてることが大切です。
採材とは太さ長さを揃える

丸太集積所に運ばれてきた木を、製材工場からオーダーされた長さに伐り揃える仕事を採材と言います。
オーダーは、主に下記が指定されます。
- 樹種
- 太さや長さ
- 節や曲がり腐れ等の品質
それぞれで価格単価が決められてます。
「一本の木からどのような丸太にするのか」の採材技術で、山林全体の価値が変わります。
積込みと発送

造材がすすみ一定数の丸太が積み上がると、丸太集積所から搬出トラックに積み込みます。
効率よく積込みしやすいように丸太を積み上げるのも大切です。
丸太集積方法が適切でないと、崩落したり陰になって死角ができたりします。
無駄な動きが発生して危険性が高まります。
発送時には作業員が丸太本数を計測しています。
重機で轢かれたり巻き込まれる事故が多いのは、丸太集積所です。
トラックの動きを確認して安全を確かめます。
早く安全に積込みして発送することが、丸太集積所で求められます。
林業造材の昨今

古くから造材は、人力や馬を使った作業が中心でした。
今も過酷な肉体労働のイメージが強く残っています。
造材機械化は数十年前からすすめられてきました。
この十年ほどでハーベスタ、プロセッサなど、高性能機械が急速に普及し始めてます。
昔は現場に行くことすら大変…

40年以上前は、造材現場へ行くまでの道路が未整備でした。
公共道路も舗装が少ない時代です。
林道に雨が降ると、たちまち水たまりや路肩決壊が当たり前でした。
林道崩壊は造材の生産性を大きく下げることになります。
機械力が向上した今は、重機で林道整備したり新道を付けることがかなり楽になりました。
飯場(はんば)方式で造材していたことも
昔の道路条件では、自宅から現場までは数時間かかることも多く、毎日帰宅してられません。
現場で寝泊まりする”飯場(はんば)”というものを設けて、造材していました。
大きな現場だと3ヶ月や半年もヤマにこもることもあります。
作業員は一年中、ほとんど自宅に戻らずヤマで過ごす人も多かったのです。
高度経済成長により丸太量が求められる時代でした。
今よりは外国産木材の脅威が少なく高単価で多量に木材需要がありました。
豊富な人的労働力があったことも飯場方式をとる要因でした。
投資された山林道路

現在は、国道などの生活道路がきれいに整備されてますよね。
林道にも乗用車が通行できるような立派な道路がたくさんあります。
日本全国の林道にはこれまで、多額の投資が行われてきました。
林道整備や治山工事に多くの資本が投入されたことで、以前よりも早く安全に山奥まで行けるようになりました。
よく見ると林道から枝分かれするように、古くに使用された作業道が点在します。
整備すれば十分に使うことができます。
過去に山林に投入された資本は、決して無駄になっていません。
立木や林道が財産となって今も残っています。
林業高性能機械で工程が変わった

現在の造材作業のほとんどが、機械や重機操作です。
造材は、肉体を酷使する労働でなくなりました。
林業高性能機械といわれるハーベスタ(木を伐る)や、グラップル(木をつかむ)が使われています。
十年前なら木の長短をそろえる玉切りと枝払いは、チェーンソーを持った人力作業でした。
ハーベスタなら枝払いして、正確な寸法で玉切りが素早くできます。
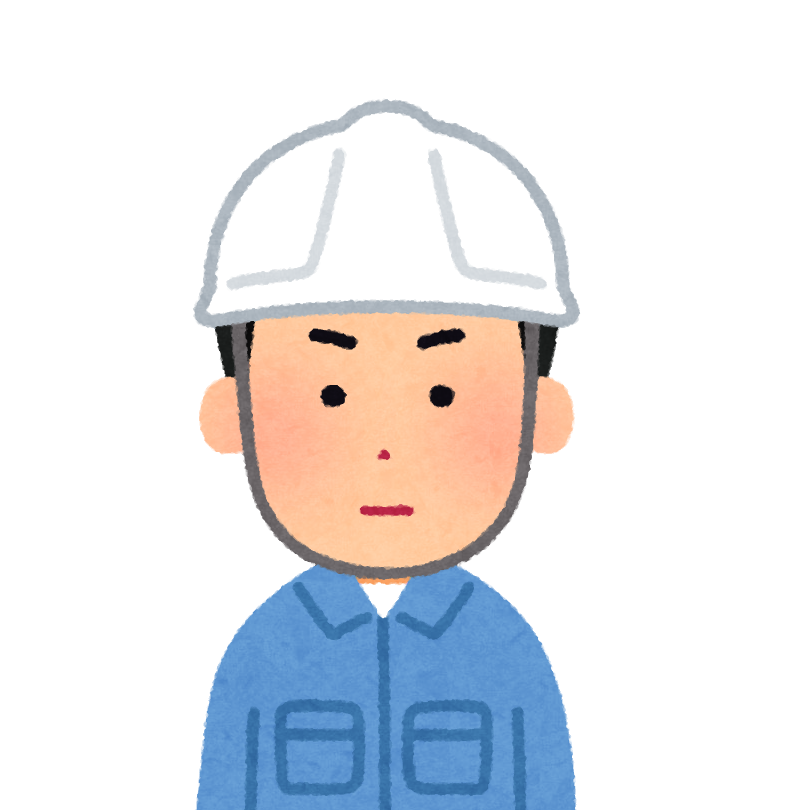
私はチェーンソーで、玉切り専門でした!

今はその作業自体がありません…
わずか10年ほどで、高性能機械化により造材の作業工程が変わりました。
高性能な能力を引き出す計画
地形が険しい日本国内の山林では、すべてを重機機械化することは不可能です。
重機が入れない条件の地形もあり、マンパワーが必要な現場もたくさんあります。
無理に重機を投入しようとすると、かえって時間や費用がかかる失敗例もあります。
一方で、建設工事の重機と比較して林業高性能機械はボタン数が多く、オペレータは慣れるまで操作が難しいです。
オペレーターを育成するためには時間がかかります。
最新機械の性能を引き出すためには、現場状況を把握して最適な計画をたてる能力が大切です。
このことが今、造材業者に求められています。
林業造材の見通し

これからの林業は温暖化対策や環境重視で、木を植えることや育てる仕事が多くなるでしょう。
育林では、間引きとなる間伐が必要です。
伐りだされる細い間伐材を、丸太資源として大切に使っていくことも大事です。
全部を伐る皆伐よりも、間伐は残す立木もあるので非効率です。
危険なかかり木を発生させるリスクも高まります。
間伐では効率よく安全に伐りだす造材技術が求められます。
間伐技術はココにも活きる
ひと昔前には伐採と聞くと自然破壊がイメージされてました。
間伐技術はこれからも活きてきます。
巨大化する台風やこれまでにない強風で、自然災害が多発してます。
豪雨による洪水、地震による地滑りや土砂崩れも増えた気がします。
甚大な被害は街や住宅地だけではありません。
山林内でも倒木や林道崩壊が多発しています。
被災した山林を復活させ整備するには、山仕事に精通した技術知識が必要です。
少なくなってしまった林業従事者は、二次災害を防ぐ専門的な知識技能を持っています。
立木から丸太をつくる造材は素材生産していく他にも、ヤマの災害復旧などで今後も必ず必要な仕事です。


